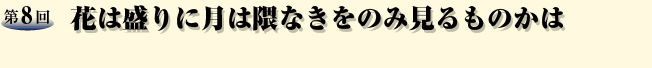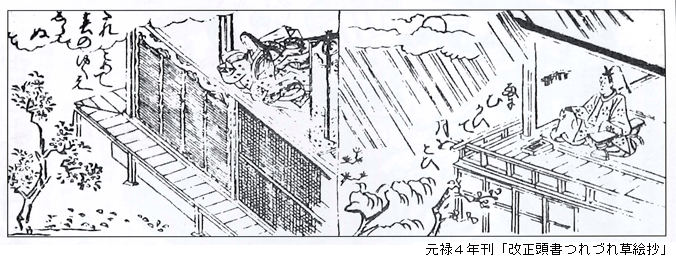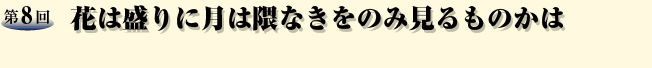
わが国では古来から花鳥風月、さらに集約して花月が自然美の代表的対象物として多くの詩歌に詠み込まれ、ここに作者の美意識を端的に見出すことができます。そこで、今回は、『徒然草』にみる作者の美意識を考えてみましょう。
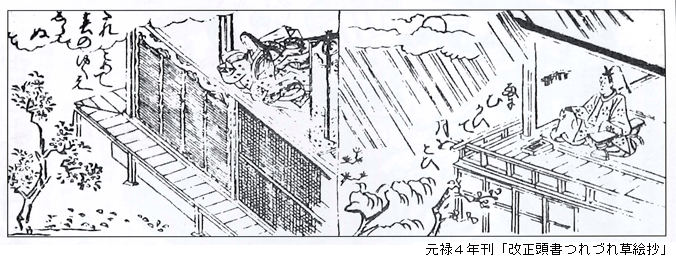 |
 |
『徒然草』第一三七段は、冒頭 に、
花は盛りに、月は隈(くま)なきをのみ見るものかは。 |
|
と述べますが、この一文こそ、兼好法師の美意識が最も端的に表現されたものとして、古来たいへん有名になっているものです。「花」即ち桜の花は今を盛りと咲き誇る満開の花だけを、月は少しのかげりもなく輝いている月だけを、すばらしいとして見るものであろうか、いやそうではない、と言っているのです。ここでは、誰しも美的鑑賞の対象物として賞賛する満開の桜花や、一点の曇りもない月だけが、美としての評価を得るものではなかろうという、通常の美的価値規準に対する見直しを迫っているのです。
では、満開の桜花、曇りなき月のほかに、どのような桜花や月に美が見られるというのでしょうか。第一三七段は、続いて、
 |
雨にむかひて月を恋ひ、垂(た)れこめて春の行方知らぬも、なほあはれに情深し。咲きぬべきほどの梢(こずゑ)、散り萎れたる庭などこそ見所(みどころ)おほけれ。
|
と述べます。月を見ることのできない雨空に向かって月の姿を慕ったり、簾(すだれ)を垂れ、その中に閉じこもって、春の陽気の移り行く様子を知らずに過ごすのも、やはり優雅で情趣深く、また、今にも花が咲きそうな桜の木の梢や、桜の花が散り萎れて地上におかれている庭などは、特に鑑賞すべき点が多いものだ、といって、これらが「花は盛りに、月は隈なき」以外に見るべき美であるというのです。ここでは、満開の桜花や少しの曇りもない月という、完全な状態に美を認める、通常の美意識に対して、雨中に月を想像したり、簾中の部屋で春の季節の進行に気づかなかった仇という状態、未開の桜花や庭上の落花など、通常は実の対象としてとらえ難い側面に対して、敢えて情趣を感じ、美的鑑賞の価値を認めているわけです。このことは、つまり、満開・満月という完全なものに美を認める通常の美意識に対して、未見のもの、未開のもの、頼落したものなどに美を認める、いわば未見美・未開美・頼落美ともいうべき、完全実に対する不完全実の価値が主張されている、ということになります。
以上のような『徒然草』にみる兼好法師の美意識は、従来には見ることのできなかった側面に実の光を照射して、新しい実の世界を開拓したわけですが、これは、室町時代の正徹・心敬・東常緑など、後世の文人たちにも高い評価を受け、継承されて、日本人の美意識を大きく深化させることとなります。もっとも、江戸時代になると本居宣長から厳しい批判を受けることになりますが、兼好法師の主張した美意識が、わが国の文芸にみる美意識の展開史の上に大きな画期を与えたことは無視することはできません。
ところで、兼好法師が、完全実に対する不完全美を主張するという独創的見解を提示することができたのは、固定的観念から脱却し、新しい視座に立つ視点を確立し得た、柔軟な思考を持つことができたからだと思います。恐らく兼好法師は、万物流転という無常観に徹するところから、「美」 の対象物も移り変わる存在であること、従って、完全も不完全も無常の一様態であり、存在の本質からみれば完全も不完全も等価であって、完全に美があれば不完全にも美があるべきだという、美に対する無常観的認識のもとに、不完全美を主張するにいたったのであろうと考えられます。
兼好法師の美意識論は、一つの思念に徹底することから、従来にない新しい世界が開かれることを教えるものとして、情報過多により自己を見失いがちなわれわれ現代人にとっても、学ぶべきことが多いのではないでしょうか。

|