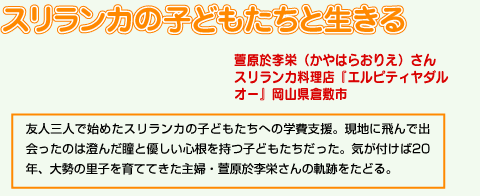
40歳のときだった。新聞で大阪を拠点とする日本の僧侶たちの活動を知った。スリランカの貧しい子どもたちに学費を送ろうというそのプログラムに萱原於李栄さんは注目した。実はそれまでもセネガルの子どもを支援するチャイルドホストには参加していた。月額5,000円のそれは、里親側から現地の子どもへは手紙ひとつ出せないきまりとなっていた。子どもから来る手紙も年に一度。なにか不自然な気持ちを抱いていた。 「必要経費はともかく、余分に中抜きされているような印象でした。それに比べてこのスリランカヘの援助は月額2,000円で、子どもたちに会いに行くツアーなどもある。どうせやるならこつちかなと思ったんです」 友人2人と組んで、3人でスリランカの子たちの里親となった。主婦として忙しく働いてきたが、娘2人も大きくなって生活に余裕が出てきたころだった。送金だけの里親では飽き足らず、友人たちと現地へと旅行してみた。これが20年という長きに渡るスリランカとのつきあいの始まりとなった。 訪ねたのはコロンボ。空港から車に乗って市内へと向かうのに、象や馬の間を走るような有様にまず驚いた。貧しい人々の剥き出しの生活がそこにはあった。バブルの好景気に沸く日本とはたいへんな違いだった。訪問先では瞳を輝かした子どもたちが出迎えてくれた。萱原さんは子どもたちに会って「恥ずかしくなった」という。 「いままで自分が生きてきたのが恥ずかしくなったんです。日本での私は子どもを置いて友達同士で旅行に行ったり、美味しい物を食べたりと、したいことばかりしてきた。いっぽうではこんなに貧しくて学校に行きたくても行けない子どもたちがいるのに自分はこんなことをしていていいのかと思ったんです」 子どもたちへの援助は原則1年。しかし「顔を見てしまうとそうはいかなくなった」スリランカの子どもたちはとにかく可愛かった。素直で正直で、これに萱原さんは感動した。友人2人もその気持ちは同じだった。 里子を増やした。スリランカの物価ならば主婦の小遣いでも何人かの小中学生の学費が賄えると踏んでいた。ところがとんでもないことが待ち受けていたのである。「バブルがはじけて建築関係の仕事をしていた主人の会社が倒産してしまったんです。取引先から生じた責任を全部かぶったような形での倒産でした」 さあ大変だ。自分たち一家の生活でさえ危機に瀕したというのに、脳裏にはスリランカの子どもたちの顔が浮かぶ。 「それからはもう必死でした。工事現場に出たり、清掃の仕事をしたり……」 働いたことのない主婦にはきつい労働だったが、里親としての義務感が身体を動かした。3人で500万円の融資を受け、それをスリランカの銀行に預けて基金とした。当時のスリランカの預金利息は12%。これだけの利息があれば年間約50人の子どもが学校に行ける。萱原さんたちはひたすら働き、3年半で借金を返済し終えた。 |

|

「スシルは今24歳。初めて日本に来た19歳のときは全然話せなかった日本語ですが、いまでは日本語検定の1級を受けるまでになりました」
店名はスシルさんの出身地であるエルピティヤ村から取った。萱原さんの活動は現在はこのエルピティヤ村の子どもを支援することに中心を据えている。
村はコロンボから車で3時間ほどの山の中にある。周囲の自然は大変豊かだが、人々の生活は逆に貧しい。スシルさんは萱原さんにとってはその村での「長男」。現在はこのスシルさんをまとめ役に村の子どもたち、村出身の若者たちに学費を援助している。
コロンボから山村へ。実はその切り替えには確執があった。スリランカヘの基金は現地の寺を通 して分配してもらっていた。どの子を支援するかは僧侶が決める。だが「里子に会わせて」と頼んでもなかなか会わせてくれない。やっとこさ訪問してみれば、そこはテレビがあるようなちやんとした家だった。
こんな豊かな家の子なら援助はいらないではないか。当然のことを萱原さんたちは主張した。加えて僧侶に対する不信感もあった。コロンボに行くたびに見るのは、なぜかどんどん立派になっていく寺だった。
「向こうの人は外国人からお金をもらうのは当たり前。まして日本人は金持ちだからもらうだけもらおうという発想なんですね」
しかし、自分たちが渡しているのは額に汗して働いたお金だ。無駄なことには使いたくない。このお金を本当に必要としている子はどこかにいないか。そこで同じ寺でも山村にある寺へと行ってみた。そこがエルピティヤ村だった。村には当時12歳のスシル少年がいた。村の人たちはバナナの葉を屋根にした家に暮らしていた。トイレもなければ水道もない、電気も通 っていない家ばかりだった。
 現在は「S・K基金」と命名され、毎年、文具や日用品が手渡されています。
現在は「S・K基金」と命名され、毎年、文具や日用品が手渡されています。
それからは毎年エルピティヤ村を訪ねた。里子は年に10人ずつ増えた。援助は学費だけに及ばない。文具や衣類などの学用品や生活雑貨を持てるだけ持つ、夜も勉強が出来るようにと里子の家には電気を引いた。宿泊費が惜しいのでホテルには泊まらず子どもたちの家に泊まる。里子の親たちとも交流が深まった。目標は里子たちを大学に入れること。出来れば1人は医大に入れたい。地元の僧侶は「この村からはそんな優秀な子は出ない」と首を横に振ったが、萱原さんたちは希望を捨てなかった。貧しくとも賢い子はいる。この子たちなら大丈夫。それは子どもたちと接していればわかることだった。
もちろん、苦しくないと言えば嘘になる。ただですら基金のやりくりに苦労しているところに、仲間の1人が家庭の事情からやむなく抜けることとなった。3人で力を合わせてやってきたものが2人に減る。これは大打撃だった。「潮時」という言葉が頭に浮かんだ。「でもやめられない。わたしのことをお母さんと呼んでくれる子どもたちが何十人もいるんですからね」
さらに一昨年には残ったもう1人の友人も病気をして活動を続けられなくなった。どうしようもない事態だったが、やめるわけにはいかない。村からは念願の大学生が生まれていた。手塩にかけたスシルさんは商船学校を卒業していた。萱原さんを介して倉敷市内の中学校とスリランカの里子たちとの国際交流も始まっていた。国費留学で日本の他の都市に留学で来ている子もいた。
「本当にみんないい子たちなんです」
萱原さんは語る。
「里子のなかでも日本語を学んでいる子たちには週に1回は電話をするんです。あなたたちどうしてそんなにいい子に育ったのって聞くと、お母さんのおかげだって言ってくれるんですね。私はもとから持っているのは身体だけ、頭と心の中身はお母さんが入れてくれた、なんてね。こんな言葉を聞くともっと働かなきやと思ってしまうんですよ」
スシルさんたち里子側からすれば、萱原さんたちの健康や老後が気にかかる。初めて日本に来たとき、スシルさんは萱原さんがけっして富豪などではなく、毎日パートに出ては働いている姿を見て驚愕したという。お母さんはこんなに苦労して自分たちを支えてくれているのだ。スリランカに帰ったスシルさんはその事実をみんなに伝えた。子どもたちはますます勉強に励んだ。

当時12歳のスシル少年は今24歳。私の片腕として活動を支えてくれています。
「あの地震では親をなくした子どもがたくさんいます。親戚に引き取られた子はまだいいけど、なかには海外に売られていった子もいるといいます」
出会った被災者の子のなかには、どうしても気になる子もいるという。
「忘れられないのは12歳くらいの女の子なんですが、援助はいらない、なぜなら死ぬ ことしか考えていないからって言うんです」
右も左もわからない幼い子と違い、多感な時期に親をなくしてしまった子の受けた心の痛手は大きい。萱原さんは「あの子はどうしているだろう」と彼女の幸せを祈り続けている。
昨年、ついに村から医大への合格者が誕生した。本人から電話でそれを知らされた萱原さんは「うわ−どうしよう」と、喜ぶと同時に頭を抱えてしまった。
「医大となると6年。日本で研修も受けさせてあげたいし、ますます頑張らなきゃ」
60の坂はきつい、と苦笑いする。
しかし、風向きは悪くない。スシルさんは現在は起業し、青年実業家への道を歩み出している。ごみ処理施設建設や医薬品開発などの事業提携を日本の企業からオフアーされていたり、萱原さん自身も長年の活動に対して『財団法人ソロプチミスト日本財団』から表彰を受けている。
「お母さんに楽をしてもらいたい」
スシルさんは言う。かたや萱原さんは、
「スシルには負担をかけていて申し訳ない。船長になる夢もとりあえず置いている状態ですしね」とあくまでも息子を気遣う。
むろん、家族への感謝も忘れていない。夫や娘2人の理解がなければここまで活動を続けることはできなかった。
「老後ですか? スリランカに行って暮らしてみたいですね」
いま頑張った先には、美しい自然に包まれた豊かな時間が待っているはずだ。
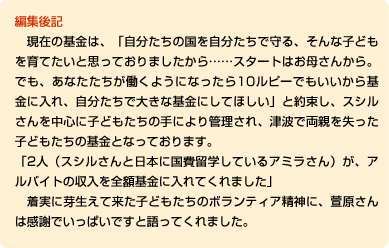

スマトラ沖地震の津波で両親を失った子どもたちにも学用品や制服を布を配布。